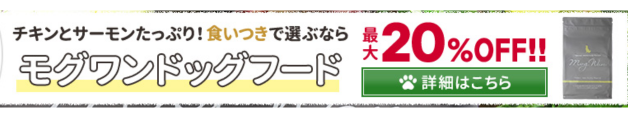肝臓病療養食の種類

- ヒルズ l/d 肝臓ケア
- ロイヤルカナン 肝臓サポート
- Dr.宿南のキセキのごはん 肝臓の健康サポート
- 和漢みらいのドッグフード 特別療法食KA(肝臓)
- Vet Solution ドッグフード 肝臓サポート
- HAPPY DOG VETヘパティック
- メディムース 犬用 肝臓サポート
- ナチュラルハーベスト レバエイドプラス(ふりかけタイプ)
どのフードが愛犬に適してるかわからない場合は以下の診断ツールで調べるのがおすすめです。
愛犬の肝臓用フード診断
10の質問に答えて、あなたの愛犬に合ったフードの方向性を見つけましょう。
診断結果
| 製品名 | どんなフードか(目的・特徴の要約) |
|---|---|
| ヒルズ l/d 肝臓ケア | 肝疾患全般に対応。銅を抑え、消化の良いタンパク質と高エネルギー。米国獣医師に最も処方されている定番。 |
| ロイヤルカナン 肝臓サポート | 銅の制限・脂質制限が特徴。味と香りで食いつきを重視し、嗜好性が高い。欧州獣医が処方する定番品。 |
| Dr.宿南のキセキのごはん 肝臓の健康サポート | 獣医師監修。鹿肉ベースで低タンパク・低脂肪。穀物不使用で自然素材中心。銅含有量も抑えめ。 |
| 和漢みらいのドッグフード 特別療法食KA(肝臓) | 薬膳思想を取り入れた国産自然派療法食。肝臓ケアに加え免疫・排毒も意識。高齢犬向き。 |
| Vet Solution 肝臓サポート | 植物性たんぱく中心・銅制限あり・高カロリー。イタリアMonge社製。グレインフリー設計。 |
| HAPPY DOG VET ヘパティック | 低脂肪・低銅・高消化性。独自のハーブ(ミルクシスル)を配合。ドイツ製の自然派寄り。 |
| メディムース 肝臓サポート | ウェットムースタイプ。食欲低下時でも食べやすい。肝臓ケア成分(BCAAやシリマリン)配合。 |
| ナチュラルハーベスト レバエイドプラス | パウダータイプの栄養補助食。肝機能支援用。いつものフードにトッピングして使う。 |
世界的に信頼されている療法食 ヒルズ l/d 肝臓ケア

ヒルズの l/d 肝臓ケアは、犬の肝臓病管理を目的として、ヒルズの栄養学者と獣医師によって開発された特別療法食です。
- 低銅設計(銅 約77%減 )
-
肝臓に病気がある犬の中には、体内から銅をうまく排出できず、肝臓に過剰な銅がたまってしまう体質の子がいます。
銅が肝細胞の中に蓄積すると、活性酸素を発生させて肝細胞を壊し、慢性的な炎症や組織の硬化(線維化)を引き起こします。
ヒルズ l/d 肝臓ケアは、一般的なフードに比べて約77%も銅の含有量を減らしているため、毎日の食事から摂取する銅を抑えることができます。
その結果、肝臓への銅の蓄積が防がれ、慢性肝炎の進行を抑えたり、肝細胞が長く健康な状態を保ちやすくなったりします。
- 高消化性炭水化物と制限された高品質たんぱく質。
-
肝臓病になると肝臓の働きが落ち、代謝の途中で「アンモニア」などの有害な物質が体に残ってしまいます。
アンモニアが脳に悪影響を与えると、ふらつきや意識の混乱などの神経症状(肝性脳症)が出ることがあります。
このフードでは、たんぱく質の量をあえて抑え、しかも質の高いたんぱく質(吸収が良く、不要な副産物を出しにくいもの)を使っています。これによって、肝臓への代謝の負担を減らしつつ、筋肉を保ち、アンモニアの発生を最小限に抑えることができます。
- L-カルニチン、抗酸化成分配合
-
肝疾患のある犬は脂質の代謝がうまくいかず、肝臓に脂肪がたまりやすくなります(脂肪肝)。脂肪肝が進行すると、肝細胞の機能がさらに落ちるという悪循環に陥ります。
L-カルニチンを補うことで、体の中の脂肪を燃やしやすくなり、肝臓に余計な脂肪がたまるのを防ぐことができます。エネルギーの生産効率も上がるため、活力の維持にもつながります。
高エネルギーで消化性の良い ロイヤルカナン 肝臓サポート

ロイヤルカナンの肝臓サポートは、犬の肝臓病の管理を目的として、獣医師の指導のもとで給与される特別療法食です。肝臓に負担をかけずに必要な栄養素を供給できるよう、栄養バランスが調整されています。
- 低銅・高亜鉛配合
-
ロイヤルカナン 肝臓サポートは銅の量を抑えながら、亜鉛を多めに配合しています。
亜鉛には、銅の吸収を抑えたり、肝細胞の再生を助ける作用があります。そのため、銅の蓄積を防ぎつつ、肝臓の修復や保護を助ける効果が期待できます。
- 中鎖脂肪酸(MCT)含有
-
中鎖脂肪酸は、通常の脂肪よりも分解が早く、肝臓を通さずに直接エネルギーとして使われる特徴があります。肝臓の働きが落ちている犬では、脂肪の消化や代謝がうまくいかず、食事から十分なエネルギーを得られないことがあります。
フードに中鎖脂肪酸が含まれていることで、肝臓に負担をかけずに、効率よくエネルギーを補給できるようになります。体力が落ちている犬や、胆汁の流れが悪い犬にとっては、大きなメリットになります。
- 高エネルギー密度
-
肝臓病の犬は、食欲が落ちやすく、必要な栄養を十分に摂取できないことがよくあります。
ロイヤルカナン 肝臓サポートは、少量で多くのカロリーが摂れるように作られています。
食べる量が少なくても、必要なカロリーを確保しやすくなります。その結果、体重の維持や筋肉の減少予防に役立ちます。
Dr.宿南のキセキのごはん 肝臓の健康サポート

Dr.宿南のキセキのごはん 肝臓の健康サポートは、獣医師である宿南章先生が開発した犬用の療法食です。肝臓の健康を維持し、肝機能が低下した犬の食事管理を目的として作られています。
- 国産無添加
-
人工の保存料や香料、着色料などの添加物を使っていないため、これらの成分を肝臓で分解・解毒する必要がなくなります。
その結果、すでに肝機能が低下している犬でも、肝臓への代謝負担を大幅に軽減できます。化学的な刺激によるアレルギーや不調のリスクも抑えられ、長期的に安定した栄養管理が可能になります。
- 白身魚や雑穀使用で肝臓に低負担
-
白身魚は脂質が少なく、消化吸収が非常に良いたんぱく源です。雑穀は血糖値を緩やかに上昇させ、消化器に優しい炭水化物です。
この組み合わせにより、肝臓が代謝に使うエネルギーが減り、肝細胞が無理なく栄養を取り込める状態が作られます。
魚のたんぱく質は肉よりもアンモニアなどの老廃物が出にくく、肝性脳症の予防にも役立つ可能性があります。
- 療法食というより自然食に近い
-
一般的な療法食は栄養成分を人工的に調整した“薬膳的”な位置づけですが、キセキのごはんは自然素材を使って体質改善や臓器の自己修復力を引き出す方向に重点を置いています。
そのため、肝臓の負担を抑えるだけでなく、全身の健康の底上げにつながる可能性があります。また、人工的な味付けがされていない分、味覚が敏感になった肝疾患の犬にも受け入れやすいという傾向があります。
和漢みらいのドッグフード 特別療法食KA(肝臓)

和漢みらいのドッグフード 特別療法食KA(肝臓)は、東洋医学(和漢)の考え方を取り入れて開発された、犬の肝臓病管理を目的とした療法食です。
一般的な療法食が栄養学的なアプローチに特化しているのに対し、この製品は、和漢植物の配合によって肝臓の働きをサポートすることを特徴としています。
- 自然原料と機能性素材が多数
-
使用されている素材は、ウコン、シジミ粉末、キノコ類(霊芝・アガリクスなど)といった、古来から肝臓を助けるとされてきた天然由来のものばかりです。
こうした素材には、抗酸化作用や胆汁分泌の促進、免疫調整作用があります。肝細胞がダメージを受けにくくなり、肝炎や脂肪肝の進行を穏やかにする方向へ働きます。
- 低タンパク・低脂肪設計
-
みらいのドッグフードは、即効性を持って症状を抑えるのではなく、時間をかけて犬の体質そのものを変えることを目的としています。
たとえば、肝酵素の数値が高くなりやすい体質の犬や、季節やストレスで体調が大きく崩れる傾向のある犬に対して、肝臓の調子が乱れにくい体内環境をつくります。 - 療法食より補完的な役割
-
和漢みらい 肝臓用は、ヒルズやロイヤルカナンのように、栄養組成を厳密に管理して病状をコントロールする療法食とは異なります。
たとえば、すでに療法食を食べている犬に対して、「療法食+和漢みらい」を併用することで、炎症を抑える働き、肝細胞を修復する力、代謝効率の改善といった追加効果が期待されます。
イタリア製の療法食 Vet Solution ドッグフード 肝臓サポート

Vet Solution 肝臓サポートはイタリアの老舗ペットフードメーカー Monge(モンジ)が開発した、肝疾患を抱える犬のための食事療法食(療法用ドッグフード)です。日本ではジャパンペットコミュニケーションズが正規輸入販売を行っています。
このフードは肝機能が低下した犬に対して、肝臓への負担を極力抑えながら、必要な栄養素とエネルギーを効率よく補給できるよう設計されています。
- 消化性が高く、便の状態も安定しやすい
-
Vet Solution 肝臓サポートは消化吸収に優れた原料を使用しており、食べたものがしっかり栄養として吸収され、不要物が腸に残りにくくなります。
その結果、便の状態が安定し、腸内ガスの抑制、体力の回復、内臓全体の負担軽減につながります。
- SOD酵素・XOS配合
-
SOD(スーパーオキシドディスムターゼ)は、体内で発生する活性酸素を分解する酵素です。肝臓に負担がかかる状態が続くと、活性酸素が過剰に発生し、肝細胞の炎症や破壊が進行します。SODを摂取することで、酸化による細胞ダメージを抑え、肝細胞の寿命を延ばす効果が期待されます。
XOS(キシロオリゴ糖)は、腸内の善玉菌を増やす働きのあるプレバイオティクスです。腸内環境が整うことで、腸から肝臓に流れ込む有害物質(アンモニアなど)が減り、肝臓の解毒負担を軽くすることができます。
- 安心のイタリア製
-
Vet SolutionはEUの厳格なペットフード安全基準が適用されています。これによって、品質のばらつきや有害成分の混入リスクが低く、安心して継続的に与えられます。
品質が安定していることで、肝疾患を抱える犬の体調が急変しにくく、治療効果のブレを防ぐ効果も期待されます。
マリアアザミで肝臓をサポート HAPPY DOG VETヘパティック

HAPPY DOG VETヘパティックは、ドイツ製の犬用療法食です。肝臓に問題を抱える犬のために、ドイツの獣医師が監修・開発しました。
- マリアアザミなどの肝保護ハーブ使用
-
マリアアザミ(ミルクシスル)は、シリマリンという有効成分を含み、肝細胞の保護と修復を助ける働きがあります。シリマリンには抗酸化作用・抗炎症作用・細胞膜の安定化作用があり、肝臓に加わる慢性的なダメージを軽減し、肝細胞の再生を促進します。
他のハーブ(たとえばアーティチョークやタンポポなど)も胆汁の流れを促進する作用があり、胆汁うっ滞による肝臓の負担軽減にも寄与します。
- 穀物不使用(グレインフリー)
-
小麦・トウモロコシ・米などの穀物を使用していないため、穀物に含まれるグルテンや難消化性のデンプンによる腸内炎症やアレルギー反応が起こりにくくなります。
これにより、腸肝連関に関わる腸内環境の悪化が防がれ、肝臓に届く有害物質の量が減少します。
- 肝疾患だけでなく胆道系にも配慮
-
肝臓だけでなく、胆のうや胆管など「胆道系」の機能にも着目して設計されています。胆道の流れが悪いと、胆汁が肝臓内に滞留し、肝細胞が傷つきやすくなります。
HAPPY DOG VETは肝機能と胆汁分泌の両方を助ける成分を含むことで、胆汁のうっ滞による肝障害を予防・緩和します。
食欲が落ちた犬に メディムース 犬用 肝臓サポート

メディムース 犬用 肝臓サポートは、肝臓の健康維持を目的として作られた、ゼリー状の犬用総合栄養食です。療法食(特別療法食)ではなく、一般的な食事として与えることができますが、肝臓に配慮した栄養設計がされています。
- 食べやすいウェットタイプ
-
ウェットタイプのフードは水分含有量が多いため、水分摂取量が少ない犬や、腎臓や肝臓に不調がある犬の脱水予防に役立ちます。
また、においや味が立ちやすく、食欲が落ちている犬でも嗅覚や味覚を刺激しやすいため、「食べるきっかけ」を与えやすいという利点があります。
咀嚼力が弱った高齢犬や病中・病後の犬でも飲み込みやすく、食事へのストレスを減らす効果も期待できます。
- 食欲低下時やシリンジ給餌に便利
-
体調が悪くて自力で食事ができない犬には、シリンジ(注入器)で給餌する必要があります。ウェットタイプでなめらかな質感のこの製品は、液体に近い状態での給餌が可能なため、無理なく投与できます。
また、食欲が戻るまでの「つなぎ」として使用することで、肝疾患の犬に必要な栄養を欠かさず補い、体力の低下を防ぐ効果があります。
- 最低限のタンパク質
-
たんぱく質を制限することで、代謝の際に発生するアンモニアなどの老廃物が減少し、肝性脳症のリスクを下げることができます。
たんぱく質の質と量が適正にコントロールされているため、筋肉量の維持に必要な最低限の栄養は確保されます。
補助食に ナチュラルハーベスト レバエイドプラス

ナチュラルハーベストのレバエイドプラスは、肝臓の健康をサポートするために高度な臨床栄養学に基づいて開発された、パウダータイプの総合栄養食です。
療法食と異なり、獣医師の処方箋は必須ではありませんが、肝機能の数値が気になる犬や、肝臓病の管理食として獣医師の指導のもとで与えられることが多い製品です。
- ふりかけ型サプリメント食品
-
主食のフードに直接振りかけて使用するため、肝機能ケアが必要な犬に対して、既存の食事内容を変えずに肝臓サポート成分を追加することができます。
食事を変えることに強い拒否反応を示す犬や、療法食の味に飽きてしまった犬にも対応しやすく、食事へのストレスを減らしながら継続的な肝ケアができます。
- ミルクシスル、タウリンを含有
-
ミルクシスルに含まれるシリマリンには、肝細胞を保護し、再生を促す作用があります。活性酸素の除去や炎症の抑制、細胞膜の安定化を通じて、慢性的な肝炎や脂肪肝などの進行を緩やかにする働きが期待されます。
タウリンは胆汁の流れを助ける成分であり、胆汁うっ滞や胆泥症のリスクを軽減しながら、脂肪代謝の改善にも寄与します。また、肝性脳症の原因となるアンモニアの解毒にも関与しています。
- 療法食との併用が基本
-
このフードは単独では栄養のバランスを満たさないため、必ず通常の総合栄養食または療法食と併用することが前提です。
肝臓のダメージが中等度以上に進行している犬では、主治療となる療法食の効果を妨げず、むしろ相乗的に補助する設計となっています。
肝臓病のドッグフードを選ぶ際の注意点

肝臓病の犬に与えるドッグフードを選ぶ際は、単に「肝臓サポート」と書かれている製品を選べば良いという話ではありません。肝臓という臓器は、代謝・解毒・栄養合成など体の中心的な機能があり、障害の種類や進行度によって必要な栄養管理は大きく異なります。
ここでは肝臓病の犬のフード選びにおける注意点を丁寧に解説します。
「療法食」であることが基本

肝臓病と一口に言っても、軽度のALT/AST上昇から、門脈体循環シャント、肝性脳症、銅蓄積性肝炎など種類が多岐にわたります。それぞれで必要な栄養戦略が異なるため、自己判断ではなく獣医師の判断のもとで選ぶのが原則です。
- 門脈シャント→タンパク質制限が必要(特に動物性タンパク)
- 銅蓄積性肝炎→銅含有量の少ないフードを選ぶ
- 慢性肝炎→抗酸化栄養素やBCAAが有用
タンパク質は「量より質」で考える
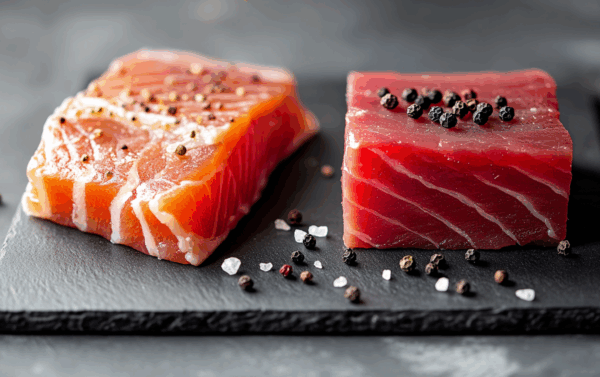
昔は「肝臓病=低タンパク」が常識でしたが、近年は不必要に制限しすぎると筋肉量の低下や免疫低下を招くと分かっています。重要なのは「アンモニアなどの有害代謝物が出にくい、高品質なタンパク質を適量摂る」ことです。
- 植物性タンパク(豆など)→代謝産物が少なく肝臓に優しい
- 動物性タンパクでもBCAA多め→筋肉維持・脳保護に有効
両方バランスよく摂る。
銅の含有量を確認すること

遺伝的に銅を蓄積しやすい犬種(ベドリントン・テリア、ドーベルマンなど)では、肝臓に銅が蓄積して炎症を引き起こすケースがあります。銅制限されたフードでなければ、病気を悪化させてしまうリスクがあります。
- パッケージに「低銅」「銅制限」と明記されているか確認
- 成分表に「銅:4mg/kg以下」など記載がある製品が望ましい
脂肪の量と質にも注意

脂肪はカロリー源としては重要ですが、肝臓での代謝負担も大きいため、病状によっては脂肪制限が必要になります。ただし、オメガ3脂肪酸(EPA/DHA)は抗炎症効果や肝細胞保護の観点からむしろプラスです。
- 「低脂肪フード」かどうか
- オメガ3系脂肪酸(魚油や亜麻仁油)が使われているか
カロリー密度が高いかどうか

肝臓病の犬は食欲不振になりやすく、痩せやすいため、少量でしっかり栄養とエネルギーが取れるよう「高カロリー設計」であることが重要です。
- 製品の「代謝エネルギー(kcal/100g)」を確認
- 通常は400kcal/100g以上が高カロリータイプ
抗酸化物質や肝細胞サポート成分の有無

肝臓は酸化ストレスに弱く、慢性炎症や線維化の進行に関わります。ビタミンE、C、タウリン、シリマリン(ミルクシスル)などの抗酸化物質や保護因子が含まれていると、肝機能の維持に寄与します。
- ビタミンE、C(抗酸化)
- タウリン(肝細胞の保護)
- シリマリン(解毒作用)
- L-カルニチン(脂肪代謝補助)
グレインフリーかどうかは補助的な観点でOK

よく「グレインフリーだから良い」と誤解されますが、穀物の有無は肝疾患に直接は関係ありません。ただし、消化性が良く、腸内環境を整える点では一定のメリットがあるため、グレインフリーにこだわるのは“嗜好と消化性のバランス”と考えれば十分です。
療法食は医師の指導のもとで与える
療法食(食事療法食)は、基本的に獣医師の指導のもとで与えるものです。 これは単なる建前ではなく、医学的・栄養学的に極めて重要な理由があります。
以下に、なぜ療法食は獣医師の管理下で使うべきなのかを説明します。
療法食は「薬に準ずる」扱い
療法食は、健康な犬にとって必ずしも最適ではない特殊な栄養バランスで作られています。例えば、肝臓病用の療法食は
- タンパク質を制限してある
- 銅の量を極端に減らしてある
- 高カロリーで代謝性に偏りがある
これらは病気を抱える犬にとっては治療の一環になりますが、健康な犬に与えると逆に栄養バランスが崩れることもあります。
したがって、薬ではないが、食事であっても「治療の一部」である以上、診断・選定・投与量の判断が医療行為の範囲に近いのです。
肝臓病の種類によって、フードの選び方も異なる
肝臓病にはさまざまな原因と段階があります。
- 門脈シャント
- 銅蓄積性肝炎
- 慢性肝炎
- 肝硬変
- 肝性脳症
これらはそれぞれ、療法食に求められる栄養設計が異なります。
例えば・・
- 門脈シャントならたんぱく質の質と量の制限が必要
- 銅蓄積性肝炎なら銅の極端な制限が重要
- 食欲不振がある場合は高カロリー+嗜好性重視
「肝臓病だからこのフードでOK」という単純な話ではなく、病態に応じた療法食の処方が必要なのです。これは飼い主の知識だけでは判断できません。
療法食にも副作用的なリスクはある
極端な栄養制限は、思わぬ副作用を生むこともあります。
- 長期間の低タンパク食 → 筋肉量の低下、免疫力低下
- 高脂肪設計 → 膵炎リスク
- 食欲不振時の食べさせ方を誤る → 栄養失調
これらは獣医師でなければコントロールが難しい領域です。
療法食は、「良いフード」ではなく、「診断と目的に応じた栄養療法」です。そのため、獣医師による診断・処方・モニタリングとセットで用いるべきものです。
逆に言えば、獣医師の診断があってこそ、療法食は正しく効きます。療法食だけで肝臓病を「治す」のではなく、あくまで支える・補うものなのです。